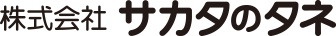![]()

![気になる外来種[その4] ブタナ](../../image-cms/header_kosugi.png)

小杉 波留夫
こすぎ はるお
サカタのタネ花統括部において、虹色スミレ、よく咲くスミレ、サンパチェンスなどの市場開発を行い、変化する消費者ニーズに適合した花のビジネスを展開。2015年1月の定年退職後もアドバイザーとして勤務しながら、花とガーデニングの普及に努めている。
趣味は自宅でのガーデニングで、自ら交配したクリスマスローズやフォーチュンベゴニアなどを見学しに、シーズン中は多くの方がその庭へ足を運ぶほど。
気になる外来種[その4] ブタナ
2025/04/08
あまり見られなくなった外来種がある反面、最近、急に日本中で幅を利かせている外来種もあります。彼らにもいろいろな事情があるようです。今回は特に、全国で生息数が増えている植物の話です。

セイヨウタンポポ
セイヨウタンポポTaraxacum officinale(タラクサクム オフィキナーレ)のことは、多くの方がご存じだと思います。それは、最も有名な外来種と言っても過言ではないでしょう。ヨーロッパ原生とされ、英語ではDandelion(ダンデライオン)といい、フランス語の「ライオンの歯(dent de lion)」が語源です。あのギザギザ葉を「歯」に見立てたのです。
一方で、「False dandelion(フォールス ダンデライオン)」と呼ばれている植物があります。意味は、「正しくないライオンの歯」=「偽りのダンデライオン」です。セイヨウタンポポが「ライオン」と呼ばれるのに対し、その植物は、日本で「ブタ」と呼ばれています。

ブタナ
その植物は、辺り一面に黄色い花を咲かせていました。これが、「偽りのライオン」と呼ばれる植物です。ブタナHypochaeris radicata(ヒポカエリス ラディカタ)キク科エゾコウゾリナ属。属名のHypochaerisとは、ギリシャ語でHypo(下)+choiros(若いブタ)の合成語です。種形容語のradicataとは、「根生の」という意味で、学名は「根出葉が若いブタに似る」という意味らしいのです。

これが、ブタナの根出葉ですが、学名の「葉が若いブタに似る」とは?いかにしてもイメージが違います。ブタナは英名では、Catsearといわれるのですが、それは「葉がCats ear(ネコの耳)に似ている」ということだそうです。こちらも同意しかねます。葉の形状は環境の影響で、地域によってブタやネコに似た葉をもつ個体群が存在しているのだ、と柔軟に解釈しておくことにします。

和名では、英名のFalse dandelionを直訳して「タンポポモドキ」とも呼ばれているのですが、ブタナの方が愛嬌(あいきょう)があります。ブタナの由来は、フランス語で「Salade de porc(ブタのサラダ)」が元になっています。この植物、家畜のよい飼料になるそうです。

ブタナの環境適応性と繁殖力は猛烈で、南極大陸以外の全ての大陸に広がっているといいます。日本でも道路際や公園、芝生、牧草地などあらゆる場所で、このようにまるで「ブタの群れ」のような姿をみます。
ブタナの起源は、モロッコとされていて、イベリア半島を経由して地中海から世界に広まったといわれています。日本への来歴は不明ですが、家畜の飼料に種子が混ざっていたと推定されていて、20世紀になってから北海道に入ったそうです。

ブタナの花は、よく見ると親しみやすいきれいな花です。大きさは3~4cm、全ての花は舌状花が頭状に集まった集合花となっています。

セイヨウタンポポと異なる点を述べるなら、花茎が長く丈夫で2~3に分枝して、その先端に花を付けることと、花の下にある総苞(そうほう)が反り返らないことです。草丈も高く、50cmくらいにはなります。

ブタナは、エゾコウゾリナ属に分類されています。この属は、日本ではブタナ以外に目立つものはなく少数派ですが、南アメリカが分布中心とされ、50種以上と推定される植物群です。花が終わると、タンポポと同じように綿毛(冠毛)を付けます。

ブタナの頭状花一つには、綿毛(冠毛)を付けた種子が50~100個くらい実ります。熟して乾燥すると、それらはタンポポと同じように風に乗って新しい生息場所にたどり着き、子ブタのように群れを作るのでした。

ブタナは、根出葉をもつ多年草です。たくさんの子ブタを産むだけでなく、適切な環境であれば、長年にわたり、親ブタの生存が可能です。当分の間、ブタナの勢いは止まらないかもしれません。しかし、直根性のため耕運に弱く、畑地に群れを作れません。森林に入ることもないでしょう。
ブタナは、動物の飼料になります。エビデンスが必要だと思いますが、薬用に効果があるようで、若い葉はサラダにするというし、根をコーヒーに代用できるともいいます。調べてみると、何だかいろいろな用途で役に立つようなので、興味深い植物でした。

次回「気になる外来種[その5]」は、その勢いはすさまじく、急速に分布を広げるナガミヒナゲシのお話です。お楽しみに。

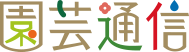
![気になる外来種[その4] ブタナ](../../image-cms/20250408_kosugi_thum.jpg)
![気になる外来種[その3] キクザキリュウキンカとオオケタデ](../../image-cms/20250401_kosugi_thum.jpg)
![気になる外来種[その2] ハゼランとタマザキクサフジ](../../image-cms/20250325_kosugi_thum.jpg)
![気になる外来種[その1] ハコベホオズキとルリハコベ](../../image-cms/20250318_kosugi_thum.jpg)
![外来の春咲き小球根植物[その4] チリアヤメとミツカドネギ](../../image-cms/20250311_kosugi_thum.jpg)